林浄因(りんじょういん)は、京都建仁寺の龍山徳見禅師が中国で僧侶の修行をしていた頃に、その弟子として仕えていた者です。龍山徳見禅師が中国での修行を終えて日本へ帰国する折、師を慕って林浄因も一緒に渡来してきました。
そしてこの林浄因が、のちに饅頭(まんじゅう)を日本に広めることとなります。
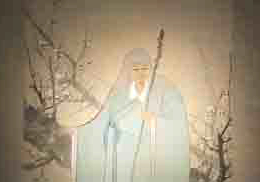
肉食が許されない僧侶のために、林浄因は中国の「饅頭(マントウ)」という肉を生地に詰めて食べる料理をヒントに、肉を小豆餡(あずきあん)に変えて包んだ饅頭(まんじゅう)を生みだしたとされています。
小豆餡には、甘葛煎(あまずらせん)という当時の甘味料を混ぜて甘さを出しました。林浄因は奈良に住居を構えていたため、奈良で饅頭作りを始めることになりました。
そしてこの頃に、地方の豪族である塩瀬家から妻を娶り、姓を「塩瀬」に改めました。
創業が貞和5年(1349年)と大変古く、歴史のある老舗。室町時代から天皇家の御用達となっている。
林浄因の作った饅頭(まんじゅう)は、小麦でできた皮の発酵した香り、ふわふわした食感、小豆餡のほのかな甘みが大好評を博し、上流階級の人々を中心に親しまれ広まっていきます。
やがて饅頭は奈良から京都に伝わり、和菓子として全国に広まり、庶民にまでその味が伝わります。
戦国期においては、織田信長、豊臣秀吉、明智光秀などの戦国武将にも愛され、特に徳川家康との関係は非常に深かったといわれています。
徳川家康との関係は天正5年(1575年)の長篠の合戦から始まっているとされ、このときには「本饅頭」という逸品が献上されています。そしてこの本饅頭で戦勝祈願をして以来、本饅頭は「兜饅頭」と名称を改めて親しまれることとなりました。
そして徳川家康が江戸において幕府を開いた折には、饅頭を商いとしていた林浄因の一族が江戸に住居を移し、将軍家御用達として饅頭を献上したと伝わります。

林浄因から始まったとされる饅頭は、今日においては誰もが知る日本を代表する和菓子として知られ、また愛されています。

そして東京に居を構える「塩瀬総本家」は、林浄因が作った饅頭の味を現代にまで守り伝え続けています。
日本最大級の流通規模を誇る楽天市場・アマゾンの、饅頭の売れ筋・人気ランキング情報です。楽天市場では、白あんの上品な味わいが魅力の博多通りもんが人気です。アマゾンは和菓子ギフトのランキングですが、栗きんとん・大福・饅頭が人気です。